木の神様を祀る伊太祁曽神社(和歌山市鎮座)のブログ。
木の国神話の社 禰宜日誌
[PR]
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
参拝の作法
年が変わると多くの方が神社仏閣に初詣にお参りされることと思います。
社頭で見ていますと、お参りの仕方はひとそれぞれに違います。
手を合わせて拝む人
2回手をたたいて頭を下げる人
1礼して目を閉じて念じる人
・・・
「神様を敬い拝む気持ちがあればそれで良い」といえないこともありませんが、きちっとした作法がありますので覚えておかれるほうが良いでしょう。
煤払い
12月13日は「煤払い」でした。
煤払いは、正月を迎えるにあたって家の内外を大掃除することをいいますが、もともとは単なる掃除ではありませんでした。
また、煤払いを行う日も12月13日ではありませんでした。
大雪
今日は二十四節季の1つ 「大雪」 です。
「おおゆき」と読んでしまった方、間違いです。「たいせつ」と読みます。
二十四節季と言われるとピンとこない方も多いと思いますが、一般に良く知られているものには「立春」「夏至」「大寒」などが挙げられます。
御神札(おふだ)の祀り方
神棚を祀っているご家庭では、年末には御神札を新く変えられて、新年を迎えられることと思います。
神棚を祀るのは、家庭に神様をお祀りすることで、家内安全・家族の健康を守ってもらうという意味があります。
毎朝、神棚に手を合わせることで、日々の恩恵に感謝する、その表れでもあります。
最近、「家内安全のお守りはないですか?」と参拝者に聞かれることがあります。
「お札をお祀りください」というと、「神棚が無いから・・・」と敬遠されることがありますが、本来「家内安全のお守り」というのがおかしいと思っています。
お札もお守りもいずれも神様の恩頼(みたまのふゆ)を頂いたものです。
お守りは、身に付けて持ち歩くことができるように、お守り袋に入れた「お札」です。
家を守るのに持ち歩く必要はありませんから、「お札」が正しいと思うのですが・・・。
貴方の注意力だけで万全ですか?
自動車の増加に伴い、年々事故も増えています。
特に悔やまれるのが、本人には何も非が無いのに巻き込まれた事故。
追突、玉突き、相手の不注意・・・。
一般に自動車を購入したときにはお祓いを受ける方は多いですが、その後はせいぜい年頭にお守りを変えるだけではないでしょうか?
交通安全祈願講では、毎月1日に執り行う月次祭に併せて交通安全祈願を行っています。
講員の方の自動車番号を神前に供えて行うものです。
亥の置物
明年歳旦より頒布する木彫りの置物(見本)が届きました。
この置物は、4月の木祭りに奉納されたチェンソーカービングの「昇り亥」を参考に奉製したオリジナルです。
(写真の置物は見本であり、実際とは若干仕様が異なる場合があります)
今日から師走です
いよいよ12月、師走です。今年も残りわずかとなってきましたね。
今月の祭礼は以下の通りです。
1日 午前9時 月次祭
10日 午後7時 冬季祭
15日 午前9時 月次祭(奥宮)
23日 午前10時 天長祭
31日 午後4時 大祓
31日 午後5時 除夜祭
今月の戌の日は 11日(月・赤口)、23日(祝・友引)です。
亥の森祭
亥の森は神社の南東約400mの、田圃の真中にあるこんもりとした森です。
(右写真参照)
この中に、三生神社という小さな祠があり、五十猛命、大屋津比賣命、都麻津比賣命をお祀りしています。
三生神社は伊太祁曽神社の摂社です。
この場所は、旧鎮座地である、現日前宮の地より現在の鎮座地にお遷りになられる間に、お鎮まりになられたところと伝えられています。
毎年、旧暦の10月初亥日に祭典を行うことになっており、今年は11月30日がこの日にあたります。
お宮だより 12月号
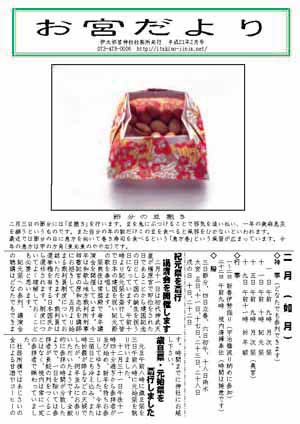 お宮だより12月号を発行いたしました。
お宮だより12月号を発行いたしました。
「お宮だより」 は神社の今月の祭典・行事の案内や、先月の行事やお祝い事でのご参拝等の報告を記載した社報で、毎月1日に発行しています。
神社公式ウェブページでもご覧いただけますが、「ときわ会(崇敬会)」会員の皆様には毎月送付いたしております。
「ときわ会」は、木の神・いのち神である五十猛命の御神徳に預かる崇敬会です。
会員の皆様には「お宮だより」送付のほかにも、年頭には神札、誕生月には誕生守り(個人会員のみ)の送付などを行っています。
他にも「お宮だより」に掲載されない諸行事の案内なども送らせて頂いております。
是非一度ご入会をご検討ください。
先ず神事
新嘗祭を終えて授与所に戻ったところで、ほほえましい参拝者を見かけました。
境内には池があり鯉が泳いでいるため「鯉の餌」を置いています。
これがなかなかの人気者で、子供は勿論、大人も結構求めて餌をやっているようです。
その参拝者は子供連れで、どうやら一の宮巡拝をされている方のようでした。
一の宮の朱印帖を授与所に預けてお参りに行かれたのですが、子供が石段横にある鯉の餌を見つけました。
「鯉の餌」やりた~~い
そういう声が聞こえてきます。
親御さんの返答はこうでした。
「まずお参りしなさい」
あたりまえのことと思われた方も多いかと思いますが、そうでない参拝者も割と多く見られるのが現状です。
神社にきて、「どんぐり拾い」や「鯉の餌やり」に興じて、最終的にお参りもせずに帰ってしまう人、割といるんですねぇ。
そういう光景を時々見ていますから、今日のこの参拝者にはほほえましさを感じました。
子供さんも素直に親御さんの言葉に従って、参拝されていましたしね。
新嘗祭
今日は新嘗祭です。
新嘗祭(にいなめさい)は、今年収穫された新穀に感謝する祭典です。
宮中では、天皇陛下が新穀や新酒を皇祖神である天照大皇神をはじめ、天神地祇にお供えし、共に食する儀式が執り行われます。
古代は11月下卯日に行われていましたが、明治以降は11月23日と定められました。
戦後はこの日を「勤労感謝の日」として祝日にしています。
社会体験学習
七五三詣
今日、11月15日は七五三詣の日です。
三歳が髪置き
五歳が袴着
七歳が帯解き
と、子供の成長を祝う儀式を行う日です。
本来は数え年でのお祝いでしたが、近年は満年齢での参拝も増えています。
また11月15日ではなく、周辺の土曜日・日曜日に家族揃ってお参りにこられる方が増えています。
時代の流れですからしょうがないですけど、せめてそれぞれのご家庭では15日に皆でお祝いしてあげてくださいね。
当神社では11月末日まで千歳飴や甘酒を準備して、皆様のご参拝をお待ちしています。







